2025.06.27
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2008.02.01
二人のお勉強シーン
最近、長女の真似をして、あっつんもひらがなの書き方練習をしているのですが、適当・・・。
まだ、2歳半なので、仕方ないのですが、メインの長女は、最近、ひらがな練習と、覚えている英単語を描くことに夢中。
どうも、ひらがなは、やわらかく描くところが多いため、アルファベットのほうが、書きやすい模様。
ミッキーの歌で覚えた、単語を、一生権目に書いていて、かけるアルファベットが増えて している亞子ですが、考えてみれば、ただ単に、自分が英語嫌いで、やっていなかっただけで、子供からすれば小さいうちなら、日本人は日本語覚えてればいいんだ!なーんて、独特な考えもないわけで、楽しいみたいです。
している亞子ですが、考えてみれば、ただ単に、自分が英語嫌いで、やっていなかっただけで、子供からすれば小さいうちなら、日本人は日本語覚えてればいいんだ!なーんて、独特な考えもないわけで、楽しいみたいです。
しかし、ひらがなの読みで、引っかかる所が必ずあるのですが、親子でもその場所は違うのだなぁと思ったり、
一生懸命に読んでいる姿はかわいいですね。
必ず引っかかるのが、「ろ」と「の」
しまちゃんの本に、自分ひとりで読める本があったので、それを渡して、髪の毛を乾かしてあげていたのですが、「ろ」と「の」が出てくると、引っかかって、とまってしまうのです。
それで、そのまま教えてあげるのもひとつなのでしょうが、分からない事はまず、自分で調べるというスタイルを身に着けて欲しくて、そのしまちゃんの本を読む前に見ていた、壊れたひらがな練習帳を渡して、「ろ」のある行を頭から読ませて見ました。
そうすると、順番に行けば思い出すようで、「ら・り・る・れ・ろ」とすんなり読めたので、また本に戻らせて、「これは?」と聞いてみました、そうすればちゃんと読めたのです、また「ろ」が出てきたら、読めなくてとまってしまい、長女は、すぐ気づいたみたいで、練習帳のひらがな表を見て、「ら・り・る・れ」と読み、本に戻って「ろ!」と言ってました。
まさか、「ろ」はこうやって読まないといけないと勘違いしていないか不安だったのですが、様子を見ていると、分からなかったら、頭から読めばよいということを最初の一回で気づいたらしく、覚えれたら、練習帳を見ることはしませんでした。
とりあえず、何とか読んだのですが、面白いことに、本を読んでいて、自分の知っている単語に近い言葉が二つぐらい並んでいると、本のとおりに読まず、オリジナル単語に代えてしまうこと。
しろいと書いてあるのに、しろくてとか、別の表現に変えてしまうのは、親譲りなのかもしれません
今回しまちゃんを再開したのですが、それについてきた、ボタンを押すとそのひらがなのを言ってくれる、ひらがなマシーンというものを使って、ちょっと勉強していたら、長女が、夢中になって大声で読むものだから、やっぱり、先に寝ていたあっつんが、おきてきてしまいました
もう9時になるから、ソロソロ寝ようといっても、寝ないと二人は言っていたのですが、何とか寝てくれてほっと一安心・・・。
しかし、石焼き芋の放送がうるさくて、ちょっと、怒鳴りかけてしまいました・・・笑
まだ、2歳半なので、仕方ないのですが、メインの長女は、最近、ひらがな練習と、覚えている英単語を描くことに夢中。
どうも、ひらがなは、やわらかく描くところが多いため、アルファベットのほうが、書きやすい模様。
ミッキーの歌で覚えた、単語を、一生権目に書いていて、かけるアルファベットが増えて
 している亞子ですが、考えてみれば、ただ単に、自分が英語嫌いで、やっていなかっただけで、子供からすれば小さいうちなら、日本人は日本語覚えてればいいんだ!なーんて、独特な考えもないわけで、楽しいみたいです。
している亞子ですが、考えてみれば、ただ単に、自分が英語嫌いで、やっていなかっただけで、子供からすれば小さいうちなら、日本人は日本語覚えてればいいんだ!なーんて、独特な考えもないわけで、楽しいみたいです。しかし、ひらがなの読みで、引っかかる所が必ずあるのですが、親子でもその場所は違うのだなぁと思ったり、
一生懸命に読んでいる姿はかわいいですね。
必ず引っかかるのが、「ろ」と「の」
しまちゃんの本に、自分ひとりで読める本があったので、それを渡して、髪の毛を乾かしてあげていたのですが、「ろ」と「の」が出てくると、引っかかって、とまってしまうのです。
それで、そのまま教えてあげるのもひとつなのでしょうが、分からない事はまず、自分で調べるというスタイルを身に着けて欲しくて、そのしまちゃんの本を読む前に見ていた、壊れたひらがな練習帳を渡して、「ろ」のある行を頭から読ませて見ました。
そうすると、順番に行けば思い出すようで、「ら・り・る・れ・ろ」とすんなり読めたので、また本に戻らせて、「これは?」と聞いてみました、そうすればちゃんと読めたのです、また「ろ」が出てきたら、読めなくてとまってしまい、長女は、すぐ気づいたみたいで、練習帳のひらがな表を見て、「ら・り・る・れ」と読み、本に戻って「ろ!」と言ってました。
まさか、「ろ」はこうやって読まないといけないと勘違いしていないか不安だったのですが、様子を見ていると、分からなかったら、頭から読めばよいということを最初の一回で気づいたらしく、覚えれたら、練習帳を見ることはしませんでした。
とりあえず、何とか読んだのですが、面白いことに、本を読んでいて、自分の知っている単語に近い言葉が二つぐらい並んでいると、本のとおりに読まず、オリジナル単語に代えてしまうこと。
しろいと書いてあるのに、しろくてとか、別の表現に変えてしまうのは、親譲りなのかもしれません

今回しまちゃんを再開したのですが、それについてきた、ボタンを押すとそのひらがなのを言ってくれる、ひらがなマシーンというものを使って、ちょっと勉強していたら、長女が、夢中になって大声で読むものだから、やっぱり、先に寝ていたあっつんが、おきてきてしまいました

もう9時になるから、ソロソロ寝ようといっても、寝ないと二人は言っていたのですが、何とか寝てくれてほっと一安心・・・。
しかし、石焼き芋の放送がうるさくて、ちょっと、怒鳴りかけてしまいました・・・笑
PR
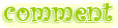
こんにちわ^^
一生懸命に読んでいる姿が目に浮かぶようです
可愛い^^
自分はというか多分青森の人は多いと思うんですが『さ行』が なまりの関係でおかしいです(笑
うちら夫婦2人ともなまってるんで
meがなまるんじゃないかと少々心配<(´ё`;)
可愛い^^
自分はというか多分青森の人は多いと思うんですが『さ行』が なまりの関係でおかしいです(笑
うちら夫婦2人ともなまってるんで
meがなまるんじゃないかと少々心配<(´ё`;)
 Re:こんにちわ^^
Re:こんにちわ^^親のいう方言は、そのままうつりますね~><
下の子なんて、方言丸出しって、妹に言われます^^;
なるべく、国語の勉強をしなくても、解けるように、標準語を使うようにしているのですが、言葉の語尾で出てしまいます><
心配するお気持ちよく分かります><
下の子なんて、方言丸出しって、妹に言われます^^;
なるべく、国語の勉強をしなくても、解けるように、標準語を使うようにしているのですが、言葉の語尾で出てしまいます><
心配するお気持ちよく分かります><
無題
失敗例をご紹介しますね。
五十音の絵の付いたポスターで
覚えさせようとしたある主婦が、
いつも鍋をお鍋と言ったばかりに、
鍋の絵の描いた「な」を
鍋の「な」ではなく
お鍋の「お」と覚えたと
テレビで昔見ました。
我が家は、やすにいが作ったので
絵は、ありませんでしたが・・・
気をつけましょうね。
子供は、純粋なので
そのまま覚えたりするので・・・
五十音の絵の付いたポスターで
覚えさせようとしたある主婦が、
いつも鍋をお鍋と言ったばかりに、
鍋の絵の描いた「な」を
鍋の「な」ではなく
お鍋の「お」と覚えたと
テレビで昔見ました。
我が家は、やすにいが作ったので
絵は、ありませんでしたが・・・
気をつけましょうね。
子供は、純粋なので
そのまま覚えたりするので・・・
 Re:無題
Re:無題そうなんですよね!
一度、勘違いした文字などを訂正しようとすると、
「これがいいの!」とか
「こっちのほうが、使いやすい」とか・・・
よく分からない言い訳されて、直そうとしなかったりするので、
なるべく変な癖はつけないようにしようと思っています。
おなべとか、「お」のつくものは、単語見た際に、どちらの子供も
「お」をつけて、言っているので、ちょっと、ひやひやです><
一度、勘違いした文字などを訂正しようとすると、
「これがいいの!」とか
「こっちのほうが、使いやすい」とか・・・
よく分からない言い訳されて、直そうとしなかったりするので、
なるべく変な癖はつけないようにしようと思っています。
おなべとか、「お」のつくものは、単語見た際に、どちらの子供も
「お」をつけて、言っているので、ちょっと、ひやひやです><
こうやって覚えていくんですね。
そっかー、こうやって子どもって
字を覚えていくんですね。
亞子さんのいい母親ぶりが
うかがえていいなぁと思いました。
あえて手を出さず、見守るところが
親のあるべき姿なんだと
さてうちの子はどこで躓くのかしら。
字を覚えていくんですね。
亞子さんのいい母親ぶりが
うかがえていいなぁと思いました。
あえて手を出さず、見守るところが
親のあるべき姿なんだと
さてうちの子はどこで躓くのかしら。
 Re:こうやって覚えていくんですね。
Re:こうやって覚えていくんですね。大きくなってくると、不思議と文字に興味を持つみたいです。
覚えていることをほめられるのがうれしいのか、一生懸命に、覚えて、読んでいます。
読めるのが面白いのかな??とも。
子供の勉強スタイルについては、あれこれ指示して、固定概念等もって欲しくなかったからです。
1+1=2が、昔からの日本の勉強スタイル
1+□=2は、欧米スタイル
というのを高校生の頃にみてからでしょうか。
言えば簡単なのですが、自分で考えて判断するという能力がつかないような気がするので、考える力を身につけさせたいなぁ~と。
教えてほしいといわれれば、教えてあげたいのですが、まずは自分で調べようというスタイルにしてほしくて。
一応、今は楽しんでるみたいです^^
ちなみに、小学校の入学祝に、今は国語辞書などの辞書を贈るとよいとか。
何でもまずは調べてみようという習慣をつけるためとかで。
それを何かで読んで共感したので、取り入れてみました^^
最初は、辞書って・・・って思いましたけど、理由を見て納得しました^^
子供は、自分のものって思わないように、あえて、放任です^^;
こけたり、イスから落ちたり・・・予測できて、ぶつかる事がないなと、判断したものは、そのまま体験させてます。
夫には、びっくりされますが^^;
体験すれば、それが危ないと、身にしみると思いますし。
でも、キケン状況ではさせてませんよ^^
でも、ずぼらもかなりあるかも・・・。
食器類も、自分で食べたいなら、そのほうが私もさっさと食べられるし・・・で、自分でうまく行くのを探したぐらいですから^^;
覚えていることをほめられるのがうれしいのか、一生懸命に、覚えて、読んでいます。
読めるのが面白いのかな??とも。
子供の勉強スタイルについては、あれこれ指示して、固定概念等もって欲しくなかったからです。
1+1=2が、昔からの日本の勉強スタイル
1+□=2は、欧米スタイル
というのを高校生の頃にみてからでしょうか。
言えば簡単なのですが、自分で考えて判断するという能力がつかないような気がするので、考える力を身につけさせたいなぁ~と。
教えてほしいといわれれば、教えてあげたいのですが、まずは自分で調べようというスタイルにしてほしくて。
一応、今は楽しんでるみたいです^^
ちなみに、小学校の入学祝に、今は国語辞書などの辞書を贈るとよいとか。
何でもまずは調べてみようという習慣をつけるためとかで。
それを何かで読んで共感したので、取り入れてみました^^
最初は、辞書って・・・って思いましたけど、理由を見て納得しました^^
子供は、自分のものって思わないように、あえて、放任です^^;
こけたり、イスから落ちたり・・・予測できて、ぶつかる事がないなと、判断したものは、そのまま体験させてます。
夫には、びっくりされますが^^;
体験すれば、それが危ないと、身にしみると思いますし。
でも、キケン状況ではさせてませんよ^^
でも、ずぼらもかなりあるかも・・・。
食器類も、自分で食べたいなら、そのほうが私もさっさと食べられるし・・・で、自分でうまく行くのを探したぐらいですから^^;
最新記事
最新コメント
[05/16 すず]
[05/13 booh]
[05/10 べりー]
[03/17 booh]
[01/07 booh]
[01/03 べりー]
[12/28 やすにい]
[12/21 やすにい]
[12/14 booh]
[11/10 booh]
お勧めサイトさま
最新記事のフィルム
amazonブログパーツ
ブログの評価 ブログレーダー
フリーエリア
プロフィール
HN:
亞子
年齢:
48
HP:
性別:
女性
誕生日:
1976/08/05
職業:
主婦
趣味:
手芸・クラフトつくり
自己紹介:
4歳の女の子と2歳の男の子を持つ、第一次反抗期真っ只中の育児日記を書いていきます。^^
カレンダー
MicroAD

 管理画面
管理画面




